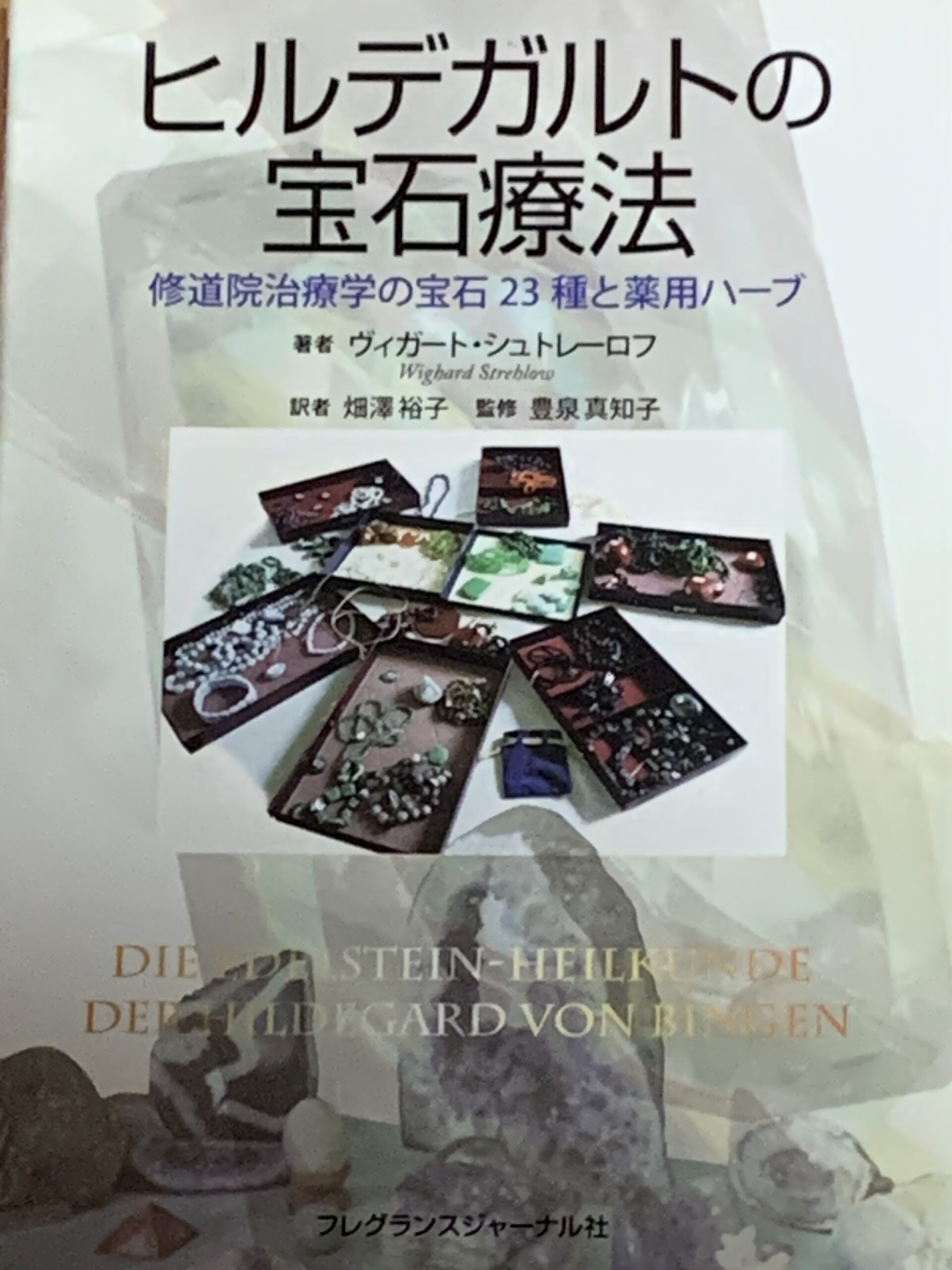FC2ブログのほうで一度載せましたが一部項目を加えたり変更したりしたものの再掲になります。
ラサシャーストラとは水銀を含む金属、鉱物、宝石などを加工して内服しやすい形にして薬として使用する、鉱物薬学のことです。内科学と外科学の古典であるチャラカ、スシュルタと比べると比較的近世に発達しました。
これらアーユルヴェーダの内科、外科の古典書は植物性生薬を原材料とした薬が中心ですが、植物は特定の季節や気候、地形でないと安定して採取出来ず、採れても処置や保存を誤ると腐ったり劣化してしまうという欠点があります。
一方で鉱物薬は植物性生薬のこの欠点を補う存在で(長持ちする)、しかも効き目が強いという利点があります(体力と消化力が強くないと使えませんが)。
日本も江戸時代までは漢方で甘汞(かんこう、塩化水銀)や辰砂(しんしゃ、硫化水銀)などの鉱物も用いられていました。
日本は水俣病の経験があるためか、水銀と聞くと拒絶反応が出るのが残念ですが、少しずつラサシャーストラについても語っていけたらと思います。まずは第一歩として基本用語集です。
・ショーダナ(Śodhana、浄化)
鉱物薬学分野の薬もしくはその材料に混ざる不純物を軽減する過程は何であっても「ショーダナ」と呼ばれます。文字通りの意味では「浄化」です(アーユルヴェーダにおける「ショーダナ」は悪化したドーシャを体外に排出することであり、吐法であるワマナ、瀉下法であるヴィレチャナ、浣腸療法であるバスティ、点鼻法であるナスヤなどが該当します。同じ語句であっても使われている背景が異なると意味が違うことに注意が必要です)。
生薬の搾り汁や煎じ液などの液体と一緒に擦るか、それらの液体の蒸気に当てたり茹でたり、といった方法が行われます。
ショーダナもしくは「浄化」とは、体に対して良くない作用をするか、あるいは効果が何もないという、全ての化学的要素に対して行う、前もって必要な処置です。
ショーダナはある薬をその治療的適応の為に適合させることです。
ある薬がこの過程を終了している場合、「ショーディタ(śodhita)」と呼ばれ、これは「(既に)浄化された」という意味です。
この「浄化」とはこの過程の後、薬が99.9%綺麗であるということを意味するものではありません。ショーダナ後にはショーダナに使用されたある種の有機物が含まれていることもあります。
それ故に鉱物薬学界で化学的に純粋な薬は、更に加工されるか、人体に治療目的で投与する前にアーユルヴェーダの、あるいはラサシャーストラの(鉱物薬学の)浄化過程を終えない限りは浄化されたとは見做されません(つまり工業的に純粋な水銀を得られたとしても、鉱物薬学で必要な有機物や無機物を用いた「浄化」を終えない限りその水銀はアーユルヴェーダの鉱物薬学界では「純粋」もしくは「浄化された」とは見做されない、ということで「純粋」の意味が異なっていることに注意)。
浄化には2種類あります。
1)物理的浄化…意図的にあるいは偶然加えられた薬から原材料を物理的に取り除くこと
2)化学的浄化…その薬から毒性を消し去るために様々な原料を加えること
・マーラナ(Māraṇa、英訳はincineration、焼灼ですが意味的には「灰化」が妥当)
人体に投与する前に金属と鉱物を徐々に焼却して(容量を減じ)、灰化物(バスマ)にすることを言います。この手技をマーラナといい、このサンスクリット語の文字通りの意味は「殺害」です。
その意味するところは、一度「殺される」と決して元の金属ないし鉱物の状態には戻らない、ということです。
元の金属ないし鉱物のままでは人体に同化吸収されないので、体内の脂肪組織に吸収されるくらい微細な形にしなければなりません。このマーラナの過程で金属は全てのその物理特性を失い、治療効果を得ます。このようにしてその金属が元来持っていた治療にそぐわない副作用ないし毒性を無くします。
とはいえ、容量や、一緒に内服する飲み合わせ(アヌパーナと言い、薬を体内の微細なレベルにまで効果的に運ぶ役割を担う、運搬用の乗り物のような役目の物質。有名どころではギー、ハチミツ、白湯など)を考慮することも、安全に治療目的を適用するには必要です。
浄化された金属や鉱物が古典書に書かれているような薬草の搾り汁や煎じ液と一緒に何度も擦られ、火にかけて(容量を減じて)灰化物にする過程をマーラナと言います。
・ニルワーパ/ニシェーカ/スナパナ(Nirvāpa / Niṣeka/ Snapana, 焼き入れ )
金属を赤くなるまで熱して液体に浸けることで、金属の浄化に用いられる手技です。
・ニルワーパナ/ニルワーハナ (Nirvāpaṇa/Nirvāhaṇa)
↑上記に似ている用語ですが赤くなるまで熱した金属を液体ではなく、他の金属の上に置く手技です。
・ダーラナ(Ḍhālana)
溶けて液状になった金属を別の液体に流し込むこと。鉛、錫、亜鉛などの浄化に用いられます。
・ジャーラナ (Jāraṇa、消化)
ジャーラナとは消化の過程を意味します。これは金属水銀を加工する際に行われる工程の一つです。ジャーラナとは液化した金属や鉱石をビダヤントラ(器具の一種)の助けを借りて水銀に吸収させる工程を言います。
・バーワナー(Bhāvanā、強いて言えば細粉化?)
鉱石や金属の粉末に決められた液体〜牛乳、薬草の搾り汁、煎じ液など〜を粉末が完全に濡れるまで加え、すりばちとすりこぎで粉末が再度完全に乾くまで擦過します。一度乾いたら少量ずつ定められた液体を注いでは擦過することを繰り返し、定められた液体が粉末と同じ量となるまで完全に注ぎきり、擦過を繰り返すこの過程をバーワナーと言います。
バーワナーを終えた時には粉末(実際には粉末と、定められた液体中の固形成分の混合物と若干の水分)は蝋燭の芯のような形を形成できて、触ると柔らかく滑らかで、押せば平たく伸びて薄片になる、そのような状態となっているのが適切な状態です(この状態をsubhāvita、スバービタと言います)。
バーワナーを終えた時にその鉱石ないし金属粉末+液体だった塊でろうそくの芯のような形を取らせることができず、触るとザラザラしていて押しても薄片状にならず、押しても縁が不規則に伸びるだけのものは不適切で、バーワナーが足りないと判断されます(この状態をdurbhāvita, ドゥルバービタと言います)。
このバーワナーは浄化だったり灰化前だったり薬を丸薬にする為だったり、と様々な目的で行われる手技です。
・アーワーパ/プラティーワーパ/アーッチャーダナ(Āvāpa/ Pratīvāpa / Ācchādana)
錫などの(融点の低い)金属が溶けた後で規定通りの薬草の粉末が溶けた金属に加えられる処置をアーワーパまたはプラティーワーパ(「ラサタランギニー」という鉱物薬学の古典書による)またはアーッチャーダナ(「ラサラトナサムッチャヤ」という鉱物薬学の古典書による)という。古典書によって単語は違えど意味するところは同じです。
この手技は錫、鉛、亜鉛を灰化する際に行われます。
これらの金属を鉄製のフライパンで加熱して溶けて液状になったら規定通りの薬草の粗挽き粉末を少しずつ加えます。
フライパンで加熱したままで擦過し、薬草粉末が灰になって金属が完全に灰に吸収されるまで行います。
・アビシェーカ (Abhiṣeka)
金属が溶けたときに8秒待ってからその中に液体を注ぐ行為をアビシェーカといいます。
・ウパラ(upala、乾燥牛糞円盤)
「ウパラ」とは牛糞を円盤状に成形して乾燥させた、食物繊維を多く含む燃料のこと(英語ではcow-dung cakeと言います)で、ピシュティカ(piṣṭika), チャンガナ(changaṇa),チャーナ(chāṇa),ウトパラ(utpala), ウパラ(upala), ギリンダ(giriṇḍa), ギリンダカ(giriṇḍaka), ウパラサーティー(upalasāṭhī),ワラーティー(varāṭī)といった同義語があります。プタ(後述)で使われる燃料です。
・カルバヤントラ(Khalva yantra, すり鉢とすりこぎ)
御影石や鉄で出来ていて、舟型か丸型などがあり、鉱物をバーワナーや擦過、粉砕するのに用います。

・アムラワルガ(amlavarga、酸味薬グループ)
ジャンビーラ(Jaṃbīra)、ニンブカ(niṃbuka, Citrus medica, シトロンのこと)、アムラヴェータサ=ヴルクシャームラ(amlavetasa=vṛkṣāmla, Garcinia indica、コクムのこと)、アムリカー=チュクリカー(amlikā, cukrikā、両方ともタマリンドのこと)、ナーランガ(nāraṅga、タンジェリンのこと)、ダーディマー(Dāḍima, 柘榴のこと)、ビージュプーラカ(Bījpūraka, 柑橘類の果実のこと)、チャーンゲリー(Cāñgerī, Oxalis corniculata、カタバミのこと)、チャナカームラ(Caṇakāmla, ベンガル豆から採られる酸味の液体のこと)、カルカンドゥ(Karkandhu, Zizyphus jujuba, ナツメのこと)、カラマルダカ(Carissa carandas)、これらの生薬が一般的に酸味薬/酸味生薬グループと呼ばれています。
大抵アムラワルガという古典書の指定は実際は全て、どの地方でもどの季節でもふんだんに使える、レモンの搾り汁かシトロンの搾り汁で代用されています。
ラサラトナサムッチャヤという古典書ではこのアムラワルガに属する生薬は水銀を頂点とする鉱物薬学界において浄化(ショーダナ)、液化、消化(ジャーラナ)に有用であり、中でもチャナカームラとコクムが最上であるとされています。
・クシーラトラヤ(Kṣīratraya, 乳液三種)
植物の乳液はクシーラ(kṣīra)またはドゥグダ(dugdha)と言い、どちらも「乳汁、乳液」と言った意味を持ちます。
アルカ (Arka, Calotropis gigantia)、ワタ (vaṭa, Ficus krishna)、スヌヒー(snuhī, Euphorbia tirucalli)、この3種類の生薬の乳液をまとめてクシーラトラヤと言います。
この3つの植物の乳液は揮発性の固形物すなわちヒ素のような物質を灰化したり火にかける前に加熱での喪失を防ぐため、混ぜられて擦過するのに用いられます。
・ドゥルティ (Druti、液状化)
ある金属や鉱石が他の薬を加え火にかけることで溶かされて固体から液体になり、液体のままで保てたらその液体をドゥルティと言います。
完璧なドゥルティの条件として、
1) 入れ物にくっつかない (nirlepatva、ニルレーパトワ)
2) 液状を保つ (drutatva、ドゥルタトワー)
3) 輝きがある (tejastva、テージャストワー)
4) 最初の固形時より軽い (laghutā、ラグター)
5) 水銀に吸収されない (sūtena asaṁyogah、スーテーナ アサンヨーガハ)
の5つが挙げられます。
・ピシュティ(Piṣṭi, 微細粉末薬)
薬の一形態。浄化された鉱物や金属や有機物を特定の液体と一緒にすり鉢とすりこぎで粉砕、擦過することで作られる微細粉末状の薬のこと。微細な粉末なので吸収と同化が早く、バスマ(灰化物)と同様の効能があるものの、バスマより効き目は穏やかであるとされる。バスマと違い加熱しないため、ピシュティにする薬は元々冷性を持っていたり、特定の液体もローズウォーターなど冷性を持つものだったり、作成後も月の光にかざして保管するなど、その冷性を生かし体内の余分な熱を取るべく調薬されていることが多い。
宝石の場合、バスマにするとお金や心の平穏が失われる(原料が高価だから…?)と伝統的に信じられているので、バスマよりはピシュティの形で処方されることが多い。
・チャクリカー(cakrikā, 円盤状原材料)
バーワナーの終わった原材料としての鉱物薬を丸めて次の段階のプタ(黒焼き)に備え、火の通りが良いように丸く薄い円盤状に整形して干したものを言う。
・シャラーワ(śarāva、浅皿)
↑のチャクリカーを並べる用の素焼きの浅い皿のこと。(↓左:チャクリカーを並べたシャラーワ)

(↑右:シャラーワサンプタ(後述)を上から見たもの。)
・シャラーワサンプタ(śarāva saṁpuṭa)
1枚のシャラーワの上にチャクリカーを並べ、その上にもう1枚の同じ大きさのシャラーワを蓋として乗せ、繋ぎ目は一面にきめの細かい泥を塗った包帯状の幅の狭い細長い布で巻いて乾かすことで密封したものを言う。鉱物や有機物の灰化物(バスマ)を作るために必要な工程、プタ(黒焼き)の下準備となる。
・プタ(Puṭa、火力の単位/黒焼き)
鉱物薬を作る際に、良く黒焼き(酸素の供給がない状態にして熱を加える)が用いられ、その加熱する時間や火力の単位として使われるのが「プタ」であり、黒焼きする行為自体も意味します。
古代インドでは地面に立方体状に穴を掘り、その穴に平べったくしてホットケーキくらいのサイズにして乾燥させた牛糞(ウパラ)を燃料として半分〜3分の2くらい敷き詰め、その上に密封した素焼きの皿(シャラーワサンプタ)や、るつぼ等を入れ、それから残った牛糞を乗せて点火することで黒焼きを行います。
その火力は穴の大きさに比例しています。特定の大きさの穴に特定の動物の名前が付いていて、大きい穴ほど大きい動物の名になっています。そして固かったり融点が高かったり、加工しにくい金属や鉱物ほど大きいプタで加工し、柔らかい金属や融点の低い鉱物ほど小さいプタで済みます。
実際はこんな感じです。(左:シャラーワサンプタをウパラ、牛糞ケーキの上にセットしたプタの様子。
右:残りのウパラをシャラーワサンプタの上に乗せて点火したプタの様子↓)

この状態で点火して火が消えるまで、ウパラが残らず燃え尽きるまで加熱する行為もプタと言います。
主要なプタ)

参考文献&サイト)
1)A Text Book of Rasashastra by Dr. Vilas Dole & Dr. Prakash Paranjpe
2)RASA ŚĀSTRA by Damodar Joshi
3)A Text Book of Rasashastra (THE MYSTICAL SCIENCE OF ALCHEMY)
by Dr. Bharti Umethia & Dr. Bharat Kalsariya
4)RASAŚĀSTRA THE MERCURIAL SYSTEM by Prof. Himasagara Chandra Murthy
5)Pathiraja et al ; Investigation of temperature pattern of traditional Puta in Ayurveda Bhasma preparation, SLJIM 2014; 04(01): 224-229
6)