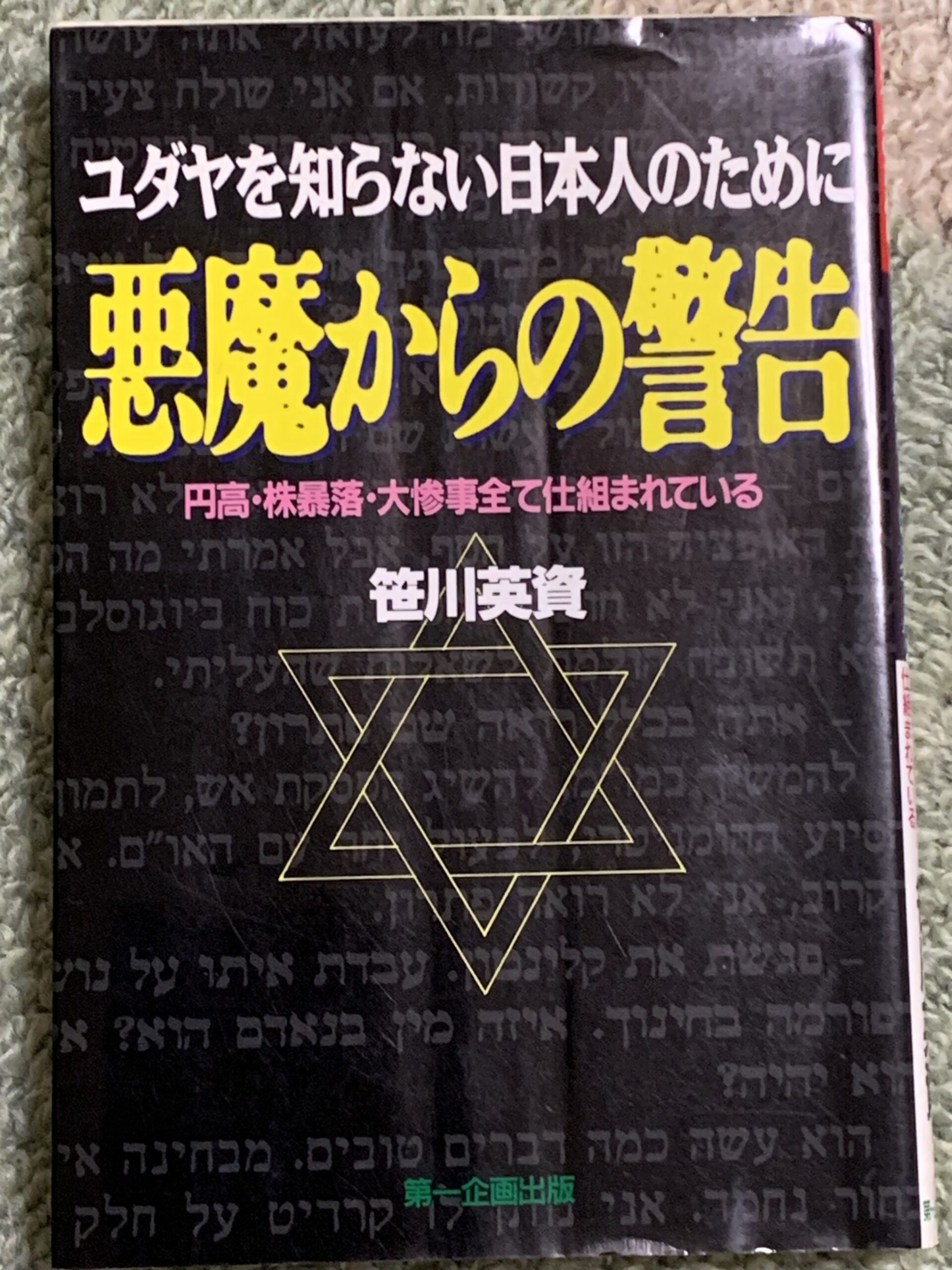※3月30日カンジダ性腰痛について追記
またまた自験例です。
先月中頃くらいから仕事量が一気に4倍に増えました。仕事が溜まっている状態というのがあまり好きじゃなかった+その仕事を終わるのを待っている人がいる。というプレッシャーを感じながら、休憩も取らずに早く出て遅く帰って。を1週間くらいしたら腰痛になりました。そう、「自分の体力気力のリミットを超えて」働きすぎるのはワータの悪化要因ですね!
と反省して、腰痛のために電車内は座っていられるほうが楽ですから、朝はもっと早く出て帰りは残業を止めて定時に上がるようにしました。
my定番腰痛アーユルヴェーダ薬である、マーシャーディーワティー(māśādhivaṭī)を6錠分3、ダンワンタラム101ソフトゲルカプセル(Dhanwantharam 101 soft gel capsules, AVP or AVS) を6Cap分3で飲みました。マーシャーディワティーはサダナンダ先生一族、サラデシュムク家に伝わる家伝薬で「器質的異常を伴わないワータ性疾患」に効くような印象です。つまり骨棘とか骨の変形を伴わないような場合ですね。ダンワンタラムのほうは同名の油を飲みやすくするためカプセルに封じたものなので、カプセルに穴を開けて中のオイルを使ってマッサージして使って良し、飲んで良し、な打ち身とか関節痛によく使われる薬ですね。これで内側から油性化してワータを鎮めようという作戦でした。
今まで大抵の腰痛はこれで良くなってましたから、今回も一時は治りかけたんですが、前の投稿で書いた、「石油が入ってこない寒い冬2年分」に備えた薪20キロ×2箱。が届いて、それを玄関から車庫に移したら一輪車を使ったんですが、それでもまた治りかけていた腰痛が悪化しました。前よりもっと。
なんというか、腰がガラスにでもなったような、ビキビキとヒビが入っていっている感がありました。
もちろん局所的・全身的オイルマッサージもしていました。関節痛に良いピンダタイラ(piṇḍa tailam)に、鎮痛といえばコレでしょ。なフロリハナのウィンターグリーンと、あとは腰の筋肉が緩んでくれれば。と思ってラベンダーのエッセンシャルオイルも混ぜて毎日のようにお風呂に入る前に塗りたくって湯船で温まって。というスネハナ(油性化)とスウェダナ(発汗法)を行っていましたがなんだか、今回の腰痛はしつこくて治りづらかったですね。というか、年を取ると傷も病気も治りにくくなるんだなーーーと思いました。
多分、前述の仕事のプレッシャーがいけなかったんだと思います。「気鬱」があって「胸脇苦満(きょうきょうくまん)」があるような場合。心身症や精神疾患の治療に長けていた昭和の名漢方医の一人、相見三郎先生はご自身が腰痛で悩まれた時に「柴胡桂枝湯」を飲まれた、と若かりし頃にどこかで読んだ覚えがあります。大塚敬節先生の本か「漢方の臨床」誌かは忘れましたが。相見先生ご自身が、先輩のとある医師にお金を貸していたそうなんですよね。相見先生もそのお金が必要だから返してほしい。でも恩がある上に目上の先輩だから催促もしづらい。という、心が強い葛藤を覚えていたら腰痛になってしまわれたそうで。
だから腰痛に柴胡剤、というのはわたしにはわりと馴染みがありました。ストレスで腹筋が硬くなって腹筋と背筋の筋力のバランスが崩れるのも良くなさそうじゃないですか。アーユルヴェーダを知る前、漢方医になりたかった頃はミーハーだったので、漢方の一流どころが集う東京八重洲の金匱会診療所で山田先生にかかっていました。その頃は花粉症でかかっていましたがたまたま腰痛になった時にわたしに処方されたのは「解労散(かいろうさん)」だったのもありまして。解労散は柴胡剤シリーズの一員の四逆散の変方です。
この処方は楊氏家蔵方や勿誤薬室方函口訣に見られ、勿誤薬室方函口訣には「解労散は四逆散の証」と言うことばが見られます。
ここで述べられている四逆散の証とは
① 大柴胡湯と小柴胡湯の中間証である。
② 腹部に胸脇苦満、心下痞硬、腹直筋の緊張がが診られる。
③ 四逆散を用いる症状は腹痛、腹満、咳嗽などである。
などが四逆散の証です。
解労散は上記に記入した四逆散に利尿、胃内停水解消効果のある茯苓を加え、他に解熱、強壮作用のある土別甲を加え、他に腹痛、強壮作用のある大棗を加え、健胃、吐き気止め作用のある生姜を加えております。
解労散は四逆散の証であるがそれより虚弱で体力低下があり、心下部に胃内停水音が診られる場合や痃癖、長年の過労が原因の病気(胸痛、悪心、嘔吐、胸脇苦満、慢性の発熱、胃、十二指腸潰瘍など)がある場合や発病期の発熱、微熱症状、腹中に塊(胆石や胆のう炎、肝炎)が
ある場合に用います。
(http://www.yanagidou.co.jp/kanpou-syohou-kairousan.htmlより)
金匱会に通っていた頃は煎じ液だったので自分で生薬をコトコト煮て煎じ液を作っていましたが、今回は地元の薬剤師さんにツムラの四逆散エキスを頼んで取り寄せてもらいました。
飲んでみて驚いたのが、すぐに「ガラスのヒビが入った感」というか、腰の「ビキビキ感」が消えたことです。
この頃には、わたしの仕事を処理する係の人も仕事が山積みで、わたしが無理をして仕上げてもそのまま処理されずに2、3日放置されていたこともあったので、なぁーんだ、そんなに急いでも結果は変わらないのか。と心から納得がいって、変なプレッシャーが消えてマイペースに戻った。という精神面、ストレス面での軽減というか、仕事の裁量権を取り戻したのも大きかったですね。
あとは生活の木に行って本を立ち読みして^^: 腰痛に良い精油、をあらためて探してシトロネラ(知りませんでした)とプチグレイン(筋肉痛に使うのは知っていた)も買ってピンダタイラに混ぜて局所マッサージもしました。
というわけで今回は「アーユルアロマ」だけではちょっと完治までは難渋して、漢方が加わったらスコーン、と快方に向かった自験例でした。
右季肋部直下にある臓器といえば肝臓ですね。サダナンダ先生は胸脇苦満を「サーマピッタの徴候」としていました。サーマピッタとはsāmapitta、アーマ(毒素)と混ざったピッタドーシャの意です。サーマピッタの徴候はいくつかありますが、
・詰まった感じ、閉塞
・不快な悪臭
・酸味を伴うゲップ
・喉や心臓周囲の灼熱感
・緑色の分泌液(排泄物)
・体の重さ
などが挙げられます。胸脇苦満は「詰まった感じ」に該当しますかね。この場合、まずはアーマとピッタを分離しないといけないので、アーマパーチャカ、アーマを消化して無くすために苦味薬とか(過剰にならない程度の)熱性薬なんかを用います。
今回の腰痛をアーユルヴェーダ的に考察すると、腰痛はサンディガタワータ、「関節に起きるワータ性疾患」の腰バージョンです。下腹部、骨盤内臓器を総括するアパーナ・ワーユ(5種類あるワータのサブクラスの内で最重要)が本来の位置(ワータワハスロータス、ワータの通り道)から逸脱して骨や骨髄や筋肉に入り込んでしまうと痛みが生じる、というのがサンディガタワータの成因です。
本来の居場所からアパーナ・ワーユを追い出したのが、最初は過労により悪化したワータ自身だとしても、引き続いていた精神的ストレスが肝気鬱滞を引き起こしたがために悪化したサーマピッタも加わっていたとしたら?辻褄が合いますね。場所的にも近いですし。ということは今度ストレス性の腰痛になったら四逆散じゃなくて、先にサーマピッタに効くグドゥーチーなんかも多めに飲んでみようかと思います。
あと今読んでいる本に、カンジダも腰痛の原因、と書いてあってびっくりしました。そう、あの真菌のCandida albicansです。
カンジダはパン、チョコレート、牛乳、チーズ、アルコール(特にビール)、白砂糖、生のマッシュルーム、酵母入りビタミン剤、スピルリナが非常に好きだそうで。逆に言うとこれらを好む人にカンジダが繁殖しやすいそうです。これらを好む人が扁桃炎ですとか歯を抜いたりなんかするときにですね、抗生物質が処方されてそれを飲むと一気に腸内のバランスが崩れてその隙を突いて日和見菌でしかないカンジダがわっと増えるそうで。
増えたカンジダは人体の角部に広がり、人間が必要とする栄養素を盗みます。当然その中にカルシウムやマグネシウムも含まれるので骨格や靭帯が弱まり、腰椎の椎間板ヘルニアを起こして神経を圧迫することによって腰痛が発生する、という機序らしいです。
【カンジダが起こす主な症状】
大脳: 頭痛、思考不能、急性/慢性憂鬱、学習不能、集中不能、神経炎、知覚異常(しびれ、チクチク感)、疲労感、立ちくらみ
目: 目の下のクマ、視覚のボケ、羞明(光が眩しい)、充血、結膜水腫、痒み
耳: 中耳炎。耳鳴、メニエール症候群、立ちくらみ、耳の痛み、耳垂れ
上気道: 蓄膿症、慢性的鼻声、鼻炎、頻繁な出血
下気道: 咳、喘息、気管支炎
消化器系: 口臭、口内炎、飲み込みづらさ、喉の違和感、吐き気、胃痛、胃炎、おなら、便秘、下痢、潰瘍、食物アレルギー
心血管系: 動悸、心臓水腫、心電図異常、皮下溢血
皮膚: 蕁麻疹、湿疹、紅斑、アレルギー性湿疹、伝染性皮膚炎、神経性皮膚炎、乾癬、ニキビ
骨格系: 関節痛、筋肉痛、関節水腫、リウマチ
その他: 貧血、膀胱炎、夜尿症
【カンジダに効果的な薬草】
紫詰草 (Trifolium pratense) 咳止め、去痰、消炎作用あり。更年期障害に良い。エストロゲンに似ている。
https://jp.iherb.com/pr/swanson-full-spectrum-red-clover-blossom-430-mg-90-capsules/118260
サントリソウ(St. Benedict thistle, キバナアザミとも言う)利尿、発汗、利胆。万能。更年期障害の頭痛に良い。抗炎症、抗がん作用もあり。
金鳳花(きんぽうげ)の根
タカトウダイ (Euphorbia lasiocaula ) 全体が有毒だが根は漢方では大戟(だいげき)と言う名の生薬として知られている。腫れ物、痛みに根を煎じた液で湿布する。虫毒や水腫、中風(脳卒中後の麻痺)、皮膚の痛みに良い
ヨモギギクの葉と花 (Tanacetum vulgare) 別名タンジー。駆虫作用、虫除けとして用いる(ピンではなかったものの配合されてるサプリ↓)
https://jp.iherb.com/pr/kroeger-herb-co-candida-formula-2-100-vegetarian-capsules/10788
アスパラガス
だそうです。パンはイーストの点でも白砂糖をどっさり使っていることからもダブルでアウトですね。気をつけよう。
でも、まあ、治ってホッとしました。もう駆け込み寺だった麻布十番のアーユルスペース楽は廃業されてしまいましたからね!季節の変わり目ですので皆様もご自愛ください。