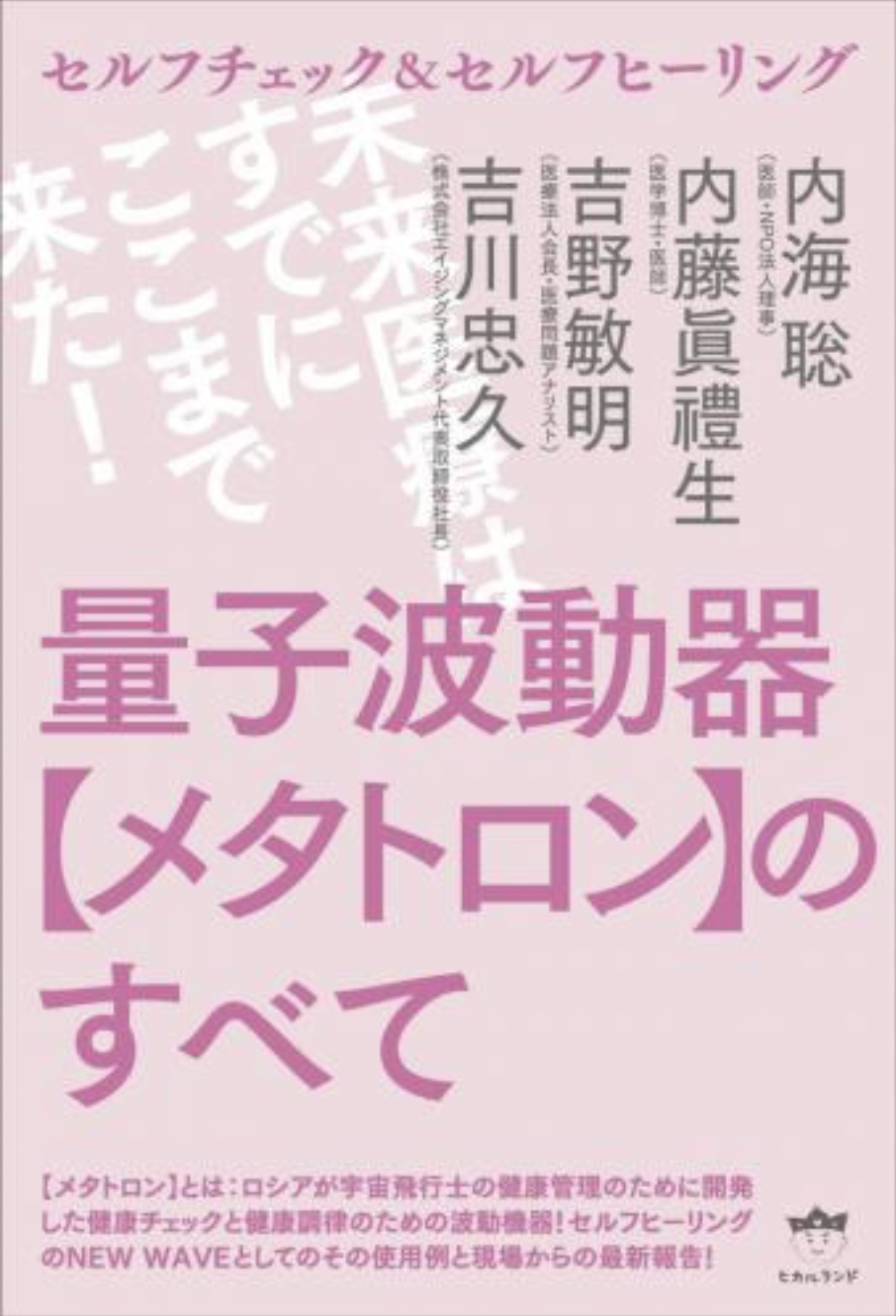★ジョーティッシュマティー全体

★ジョーティッシュマティーの幹に現れる特徴的な白い斑点

☆ジョーティッシュマティーの葉

☆ジョーティッシュマティーの花

☆ジョーティッシュマティーの未熟果

☆ジョーティッシュマティーの完熟果

☆ジョーティッシュマティーの種

☆ジョーティッシュマティーの種子油

【学名】
Celastrus paniculatus Willd.
【科】
ニシキギ科(Celastraceae)
【同義語・異名】
アグニバー(Agnibhā):花々は黄色い
Black oil plant(英名)
Climbing staff tree(英名)
ドゥルマダー(Durmadā):壊死を引き起こす
ドゥルジャラー(Durjarā):老衰を防ぐ
ジョーティシュカー(Jyotiṣkā):知的能力を啓発する/健脳薬として作用する/幹に輝く斑点が現れる/効力温性
カーカンダキ(kākandaki):実はカラスの卵に似て球形をしている
カーカーンディー(Kākāṇḍī):実はカラスの卵に似て球形をしている
カングニカー(Kaṅguṇikā):種子は雑穀に似ている
カタビ(Katabhi):種子は辛い味をしている
クシプラ(kshipra)
ラター(Latā):つる性植物である
ラワナー(Lavaṇā):多くの異常を軽減する
メディヤー(Medhyā):知能を増す
マティダ(Matida)
パンヤー(Paṇyā):貿易品目である
パーラーワタパディー(Pārāvatapadī):根は鳩の足に似ている
ピータタイラ(Pītataila):黄色い油を産する
サラスワティー(Sarasvatī):健脳薬であり水辺で育つ。サラスワティー女神のように知性を増す
スプタットワチャー(Sphuṭattvacā):皮膚に水疱を作る
Staff tree(英名)
スークシュマファラー(Sūkṣmaphalā):実は小さい
スワルナラタ(svarnalata)
スワルナラティカー(Suvarṇalatikā):花々は黄色い
ヴェーガー(Vegā):即効性がある
ヴルシャ(Vrusha)
知恵の樹(和名)
【ガナ/クラ(古典における分類)】
ガナ)
チャラカ: Śirovirecana(頭部浄化薬)
スシュルタ: adhobhāgahara(瀉下薬), śirovirecana (頭部浄化薬)
クラ)
Jyotiṣmatikula
【ラサ(味)】
辛苦
【グナ(性質)】
鋭、油、流動性
【ヴィールヤ(効力)】
温性(atyuṣṇa、熱性とする本も。)
【ヴィパーカ(消化後味)】
辛
【プラバーワ(特異作用)】
健脳作用
【ドーシャへの影響】
ワータカファシャーマカ(ワータとカファを緩和する)
【スロトガーミトワ(経路・臓器・組織行性、親和性。特に作用する部位のこと)】
ドーシャ: カファワータグナ(カファとワータを緩和する)(オイル)、ピッタ&アグニワルダカ(ピッタを悪化させアグニを強める)
体組織(ダートゥ):マッジャー、ラサ
老廃物(マラ):便、汗
内臓:胃
【カルマ(作用)】
・向知性作用(Medhya)
・理解記憶力向上(Buddhi smṛtijanana)
・悪化ワータ除去作用(Vātahara)
・知覚回復作用(Vedanāsthāpana)
・神経賦活作用(Nāḍībalya)
・顔色を良くする(Varṇya)
・視力に良い(Cakṣusya)
・頭部浄化作用(Śirovirecana)
・ワーユとアグニを亢進(Uttejaka)
・消化力向上(Dīpana)
・アーマ燃焼作用(Āmapācana)
・催吐作用(Vāmanī)
・緩下作用(Anulomana)
・心拍出力増強作用(Hṛdayottejaka)
・発汗作用(Svedajanana)
・止痒作用(Kaṇḍūghna)
・抗浮腫/抗炎症作用(Śothahara)
・難治性皮膚病を治す(Kuṣṭhaghna)
・創傷浄化作用(Vraṇaśodhana)
・腎機能賦活作用(Vṛkkottejaka)
・利尿作用(Mūtrajanana)
・強精作用(Vājīkaraṇa)
・通経作用(Ārtavajanana)
【適応(ローガグナタ)】
脳神経疾患(Mastiṣkanādīvikāra)
記銘力低下(Smṛtihrāsa)
ワータ性疾患(Vātavyādhi)
ワータ性疾患(Vātavikāra)
片麻痺(Pakṣāghāta)
顔面神経麻痺(Ardita)
坐骨神経痛(Gṛdhrasī)
発熱(Jvara)
消化力低下(Agnimāndya)
腹部腫瘤(Gulma)
腹部疾患(Udararoga)
咳嗽(Kāsa)
呼吸困難(Śvāsa)
心臓病(Hṛdroga)
顔色の異常(Varnavikāra)
皮膚病(Tvagvikāra)
難治性皮膚病(Kuṣṭha)
皮膚掻痒症(Kāṇḍū)
浮腫(Śotha)
甲状腺腫(Gaṇḍamālā)
嚢胞(Granthi)
腰痛(Kaṭiśūla)
変形性関節炎(Sandhivāta)
排尿困難(Mūtrakṛcchra)
勃起不全(Dhvajabhaṅga Klaibya)
月経異常(Ārtavavikāra)
無月経(Rajarodha)
【薬用部位】
種子
オイル
葉
【用量・用法】
種子:1-2g
オイル:5-15滴
【含有化合物】
種子にはアルカロイドとして
Celastrine
Wifornine
Paniculatine A & B
セスキテルペンアルカロイドとして
Celapanin
Celapanigin
Celapagin
セスキテルペンエーテル/ポリヨールエステルとして
Malkanguniol
Malkangunin
Celapanin
Celapanigine
Agofuran
キノンメチド/フェノリックトリテルペンとして
Celastrol
Pristimerin
Zeylasterol
Zeylasterone
石炭酸として
Acetic acids
Benzoic acid
脂肪酸として
Oleic acid
Linoleic acid
Palmitic acid
Stearic acid
Crude lignoceric acids
結晶構造物として
Tetracosanol
Sterol
葉にはサポニンが豊富に含まれ、一方、樹皮と根にはβ-sitosterol, pistimerin, zeylasteral, terpensが含まれる。
【使用例(āmayikaprayoga)】
外用)
・シドゥマクシュタ(癜風)に対してジョーティッシュマティーをアパーマールガのクシャーラ(有機灰)を混ぜた水と共に擦って7回濾して作るオイルでマッサージすると良い。
・ジョーティッシュマティーオイルとピンダラカの根を点鼻すると熱における傾眠傾向に良い
・ジョーティッシュマティーの煎じ液で傷を洗うと創傷の消毒に良い
内用)
・ジョーティッシュマティーオイルを牛乳と混ぜてスワルジカのクシャーラ(有機灰)にヒングを加えたものと共に内服すると腹水(ウダラローガ)に良い。
・精神異常(ウンマーダ)、てんかん(アパスマーラ)にジョーティッシュマティーオイルは有用である
・ハイビスカスの花とカーンジー(発酵させて酸っぱくなったお粥)とジョーティッシュマティーの葉を油で炒めたものは無月経に良い。
【処方例・主な適応】
ジョーティッシュマティータイラ(Jyotiṣmati taila)・精神異常
【注意・禁忌】
種子を用量以上に摂取すると下痢や嘔吐を引き起こすことがある。
【1行まとめ】
ワータ性疾患と消化器生殖器に良い温性の健脳薬
【臨床小話】
大抵の健脳薬は効力が冷性で消化後の味が甘いのですがワチャーと共にジョーティッシュマティーはその例外で、温性の健脳薬の一つです。
サフ准教授とシャルマ助教の本には神経変性疾患、記憶喪失、認知症、神経症、頭痛に対する選択肢となりうる、と書かれていますが個人的には使用経験はありません。
温性というよりは熱性なので消化の火を高め、カファとワータドーシャは凄まじく減らしてくれますがピッタは悪化させるので、摂り過ぎの副作用が下痢嘔吐など、ピッタ悪化症状となっています。
逆に熱性が強いのでワータとカファの異常にはとても良く効くことが予想され、古典にはウンマーダ(精神異常)としか書いてないジョーティッシュマティーオイルの適応ですが、これなら神経変性疾患に良いのならパーキンソン病なんかにも使えるのではないかなと思っていたら1例だけでしたが、症例報告がありました。↓
https://saspublishers.com/media/articles/SJAMS15372-375_ZfibYR0.pdf
62歳男性です。
6ヶ月前からの上肢の振戦、動作の遅さ、発音の不明瞭さを主訴に受診した病初期の、freshなケースでまだ西洋医学的治療もなされていない方でしたが、1週間のジョーティッシュマティーオイルの点鼻とその後のアシュワガンダ、スペイン甘草といった別の健脳薬の内服と貧血に対する薬用酒2種類の内服で主訴が全て消失し、他覚的に認められていた筋固縮も消失したという、劇的な改善でした。
この症例報告の中で、ジョーティッシュマティーは、脂質過酸化物の分解物として生成される化合物であり、脂質過酸素化の指標として酸化ストレスを反映したり、アミノ基やチオール基と反応してタンパク質変性やDNA損傷を引き起こす反応性アルデヒドである「マロンジアルデヒド(MDA)」を著明に減少させ、逆に抗酸化作用、解毒作用のあるグルタチオンや抗酸化作用に優れているカタラーゼを著明に増加させるそうです。
ジョーティッシュマティーの水抽出物は認知機能を向上させ、抗酸化作用があるという報告https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12120811/もあります。
「抗酸化」がなんだかキーワードみたいですね!
そして内服薬として処方されたアシュワガンダーhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21407960/とスペイン甘草https://www.ijbio.com/articles/nootropic-action-of-glycyrrhiza-glabra-root-extract-on-the-dendritic-morphology-of-hippocampal-ca1-neurons-in-adult-rats.pdfは共に健脳薬でもあり、神経組織を再生することが知られています。
パーキンソン病は古典ではカンパワータ(Kampavāta)ですとかヴェーパトゥ(Vepathu)と呼ばれていますが、その病因の一つに体組織の欠乏、ことに血液組織の減少があるとされていて、それで追加で処方されている2種類の薬用種はいずれも血液を増やす作用があります。
日本ですとこうした難病の方は現代医学の治療を受けて打つ手が無くなってから伝統医学だったり代替医療の門戸を叩かれることが多いですけれども、インドは国のバックアップがあるのでこうして病初期から伝統医学の治療を受けるという選択肢があって、結果も出していて大変羨ましいなと思いました。